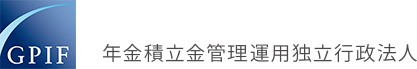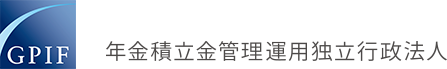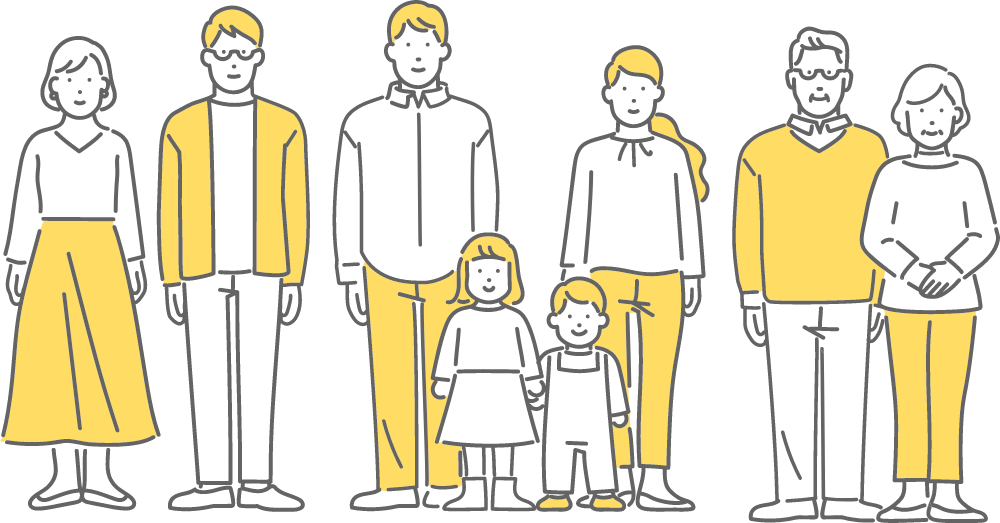運用受託機関の議決権行使に関する検証〜利害関係先とそれ以外の議決権行使の違いの検証〜
GPIFは、「スチュワードシップ活動・ESG投資の効果測定プロジェクト」の一環として、「運用受託機関の議決権行使に関する検証〜利害関係先とそれ以外の議決権行使の違いの検証〜」を実施しました。プロジェクトの完了に伴い、以下の通り、報告書を公表します。
GPIFは、運用受託機関に対して、長期的な企業価値の向上につながるスチュワードシップ活動を積極的に行うよう求めており、議決権行使についても、運用会社は受益者の利益を第一として行動するよう要請しています。
しかし、2014年に日本版スチュワードシップ・コードが策定された時点では、金融機関グループ傘下の運用受託機関において、親会社等との利益相反の懸念について組織的な対応がなされていない事例がありました。今回の分析では、そもそも過去において、投資先企業との利害関係の有無によって議決権行使の傾向に違いはあったのか、その後、運用受託機関の利益相反管理が徹底されたことで議決権行使行動が変容したかを大量の議決権行使データを用いた定量分析によって確認しました。
分析の結果、全体的な傾向(全体の平均)としては、利害関係の有無が議決権行使に影響を与えている傾向はほぼ見えませんでした。一方で、反対率が高い議案、すなわち、議案の可決・否決に大きな影響を与える可能性が高い議案については、行使傾向に違いが現れている点も一部で存在していました。例えば、2017年度より前は反対率が高い議案で利害関係先に対して寛容な行使(賛成行使)をする傾向がありました。しかしこうした傾向も、全体で見れば、時間を経るにつれて解消に向かっていることが示唆される結果となりました。
スチュワードシップ・コードなどによる政府の対応やアセットオーナーの要請を受け、運用受託機関が利益相反管理を強化したことによる影響が、実際の議決権行使にも表れてきた可能性が考えられます。ただし、個々の運用受託機関の議決権行使結果をつぶさに見ていくと、利害関係の有無による議決権行使の傾向の違いは一様ではないことも確認しました。
今回、大量の議決権行使データを用いることで、個別の行使事例の確認では観測できない利害関係先と利害関係先以外の行使の差を定量的に分析した点は大きな成果と言えます。ただし今回の分析では、運用受託機関の利害関係先の定義をGPIFが行っており、取得可能なデータの制約等により、利益相反管理が必要な全てのケースをカバーできている訳ではありません。利益相反は様々な場面で起こり得るものであり、運用受託機関によって利益相反管理の体制や、管理対象としている範囲が異なります。個々の運用受託機関の組織に合った利益相反管理の在り方については、引き続き運用受託機関と対話を続けることで、より良いかたちを追求していくことが必要です。